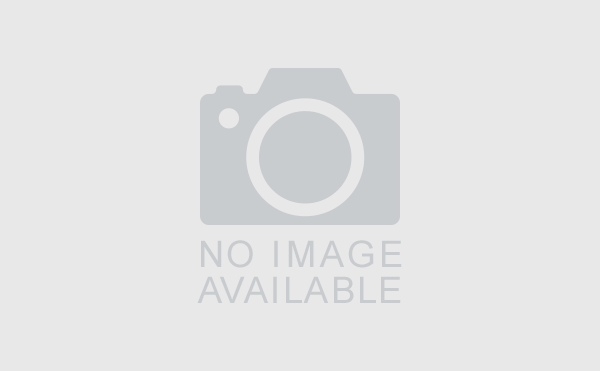マイナンバーカード
マイナンバーカードについてちょっと調べてみました。
デジタル庁によると現在は次のようになってます(3月28日更新データ)。
普及率(人口に対する保有枚数) 78%
健康保険証としての利用登録 84.5%
公金受取口座登録率 65.3%
単純に計算すると、人口のうち、
マイナ保険証を持っている割合は66%で、
公金受取口座を登録している割合は51%、ということになります。
先日新たな経済政策として生活困難世帯への給付金の支給が検討されているとか報道がありました。
給付金の支給はこれまでも何度も行われており、その度に自治体の担当者は大変だった
ことでしょう。こんな時のための公金受取口座の利用だと思いますが、51%ではちょっと
活用は難しいですね。また給付金ではなくマイナポイントでの支給案もあるそうですが、
マイナンバーカードの普及のためとか言われてしまいそうです。
とこでマイナンバーカードをどうして嫌がるかのでしょうか。
今はやりのAIに聞いてみました。その結果、
『マイナンバーカードを嫌がる理由は、「個人情報漏洩への不安」「必要性やメリットを感じない」
「手続きが面倒」「セキュリティや政府への不信」「利用シーンやメリットの説明不足」などが挙げられます。
これらが複合的に作用し、普及の大きな妨げとなっています。』、だそうです。
個人情報漏洩は絶対ないとはいえません。それはどんな制度やシステムも同じです。ただ、カードそのもの
には氏名、生年月日、住所、性別しかありません。
その程度の情報は既に漏れていると思います。個人番号を秘密にすること自体はナンセンスな
はずなのに、政府自体がそのような対応をすることによってさらに不安をあおっている気がします。
落としたら大変だといいますが、免許証、現在の保険証、銀行のカードやクレジットカードを
落としても大変ですよね。
普及が進まない原因は、テレビや新聞などの大手メディアのネガティブキャンペーンでしょう。
政府の説明不足もあるとはいっても、メディアが報道しなければ伝えるすべは限られてしまいます。
とは言っても説明不足であることは事実かもしれません。
使う機会がないという人は多いでしょう。今できる主なことは、
・本人確認、身分証明
・オンラインでの行政手続きの一部
・コンビニでの行政手続き
・マイナ保険証、運転免許証
今後できるようになることは
・iPhoneでのマイナンバーカードの利用
・国家資格の証明(現在も一部の資格はできるようです)
・民間活用の拡大、など。まだまだメリットは感じられない人は多くいると思います。
良い悪いは別として、行政のデジタル化や民間取引のオンライン化は進みます。
そしていくら反対しても昭和や平成の紙と対面がメインの時代には戻りません。
マイナンバーカードを持たなかったり返納したりしても、それは自由ですが
持たないメリットはどんどん減り、デメリットはどんどん増えます。
私は国税局を退官して2年弱ですが、国税局で相談事務をしていて感じたのは、
「これって高齢者の切り捨てじゃないだろうか」ということです。
税務の世界はe-taxに一直線です。
かつてパソコンが職場に入り始めたとき、年配の上司は部下にやらせて自ら使用しない方が
多くいました。そのまま退職した人は結局パソコンを使うことができませんでした。
スマートフォンも同じです。若い時(60歳前)に若い人に交じって使おうとしなかった
人は高齢者になってからやり始めるのは大変です。退職時に同期でLINEグループを作ろうと
したのですが、LINEをやったことがない、やるのは家族だけ(特に連絡は来ない)という
仲間が多かったのには驚きました。私の両親はパソコンもクレジットカードも持ってませんし使えません。
でも困ることはありませんでした。しかしこれからはそうはいきません。
良い悪いの問題ではありません。ついて行こうとしないと置いて行かれます。
これからはAIがその対象となるでしょう。
私はマイナンバーカード肯定派です。ただ今の政府のやり方がには疑問が残ります。
デジタル化は止まりませんがついて行けない人のためのセーフティネットは必要です。
先日マイナ保険証でそのことを感じました。その件についてはま今度。